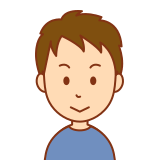
自営の方たちはケガしたり、病気をしたりして働けなくなったとき心配なことが多いよね
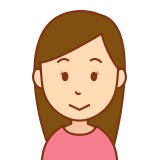
デリバリーで料理を運ぶ人もそうだけど、自営の人はたくさんいるわ
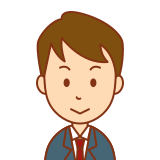
そこで自営業の方たちがはたらけなくなった時に助けてもらえる制度を紹介します。
働けなくなったらすぐの保障がいいか。長期の保障がいいか、自分の状況に応じて備えましょう。
自営業者の型は仕事中にケガをしたり、業務外でケガをして働けなくなったり、後遺障害により働けなくなった時に補償はどうなのか?年金はどうなるのか?という不安を抱えています。
そこで下記のとおり公的保険や年金などでどのような補償が用意されているのか、各ホームページを参考にまとめたのが以下になります。
| 種類 | 内容 | 備考 |
| 仕事でのケガ | 労働者災害補償保険(所謂「労災保険」)には一定の個人事業主に任意に加入が認められる「特別加入制度」があります。「労災保険の特別加入制度」には都道府県労働局長の承認をうけた特別加入団体を通じて行うことになります。これには「新たに特別加入団体を作って申請する方法」と「すでに特別加入を承認されている団体を通じて加入する方法」があります。 <保険給付の種類> ・療養(補償)給付 ・休業(補償)給付 ・障害(補償)給付 ・傷病(補償)給付年金 またその年に支払った保険料は社会保険料控除の対象となり税金上有利な取り扱いがあります。 | <参考> 厚生労働省ホームページ |
| 業務外のケガ | 仕事とは関係のない業務以外での負傷や疾病への傷病手当金の給付は、国民健康保険組合では行っていません。ただ一部の業種の国民健康組合では給付を行っている場合があります。ご自分の業種の国民健康保険について調べてみてください。 右に代表的な国民健康保険のホームページをご案内します。 | <参考> ・全国土木建築国民健康保険ホームページ ・建設連合国民健康保険組合ホームページ |
| 公的年金の障害基礎年金の給付 | 障害基礎年金の受給要件 次の1、2のすべての要件を満たしているとき 1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にある。 ・国民年金加入期間 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 ・障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。 ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。 ※日本年金機構ホームページ内「障害基礎年金はどのようなときに受けられますか」を参考にしてください。 2.保険料の納付要件 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと 3.年金額 障害基礎年金の年金額(令和4年4月分から) ※直近の年金額は各ホームページから確認ください。 (1)障害等級1級 972,250円+子の加算額※ (2)障害等級2級 777,800円+子の加算額※ ※子の加算額 2人まで1人につき223,800円 3人目以降1人につき74,600円 ※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。 ※日本年金機構ホームページ内障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額 | <参考> 日本年金機構ホームページ |
| 就業不能時に備えて | 個人事業主等で労災保険に特別加入できたり、傷病手当金制度のある国民健康保険組合に加入できる人は限られています。 個人事業主等が就業不能となったときの収入減や無収入に備えて、以下のような貸付けや金融商品の利用が考えられます。 【小規模企業共済の「傷病災害時貸付け」を利用】 小規模企業共済は、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する積み立てによる退職金制度で、個人事業主等も加入することができます。加入者には様々な貸付制度があり、その中に「傷病災害時貸付け」があります。負傷や疾病により一定期間入院した場合や、災害救助法が適用された災害等または火災、台風等の一般災害により被害を受けた場合、個人事業主等の経営の安定を図るため、低金利で事業資金が借りられる制度です。 借入額は掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。加入年数が長いほど、まとまった事業資金を借りられ、一定の計算式で得られた金額が1,000万円を超える場合、一定の計算式で計算を行って得た額が1,000万円を超えるときは、この計算を行って得た額で借入れをすることができます。 ・借入期間 借入金額に応じて、以下の借入期間となります。 500万円以下 : 36か月 505万円以上 : 60か月 ・申込受付期間 (傷病)入院した日から6か月以内 (災害)災害が発生した日から6か月以内 【日本商工会議所の「休業補償プラン」を利用する場合】 経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合(就業不能)に、保険商品で備える方法は、所得補償保険や就業不能保障保険などがあります。 日本商工会議所の会員向け所得補償保険団体契約の「休業補信プラン」には、個人事業主等でも団体保険に加入できる方法があります。 商工会議所への入会方法は各地域の商工会議所によって異なりますので、入会方法は最寄りの商工会議所にお問い合わせください。また取扱いの保険商品は商工会議所によって相違がありますので、最寄りの商工会嶬所に確認してください。 「休業補償プラン」の特徴は下記のとおりです。 ・保険金の支払対象期問が1年の「短期補償タイプ」や、60歳あるいは65歳までといった「長期補償タイプ」があります。(ともに免責期間が設定されています。) ・長期補償タイプは、免責期問が60日のものもあれば、3年といったものもあります。 ※免責期間とは保険金の支払対象とはならない期間です。 ※免責期問が長いほど保険料は割安になります。ただ免責期間中に必要となる生活資金等を準備しておく必要があります。 ※精神障害についても補償対象となりますが、長期補償タイプでの保険金の支払いは、主契約の対象期間にかかわらす最長2年です。 この保険に加入するには、商工会毒所の会員となり年会費が必要となります、ただ保険料は団体割引が適用され割安になります。 | <参考> 小規模企業共済ホームページ <参考> 日本商工会議所ホームページ ※「商工会議所保険制度」が上記ホームページからリンクされています。 |


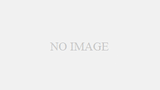
コメント